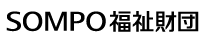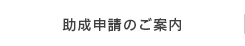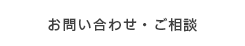第17回損保ジャパン記念財団賞 文献要旨
『病いの共同体:国立療養所多磨全生園における文化形成とその変容』
成蹊大学ほか非常勤講師 青山 陽子
国立療養所多磨全生園は、東京の西に位置するハンセン病療養所である。本書はこの多磨全生園で行った10年以上におよぶフィールドワークとインタビューデータをもとに作成された。
【研究目的と理論的背景】
本書の目的は、療養所という場で営まれた患者たちの生活活動が、集団としての連帯を生み出し文化を形成していったプロセスを描き出すことにある。とりわけ、このような活動が集団それ自身を形成するだけに留まることなく、どのようにして管理運営組織さらには一般社会へもその文化を浸透させていったのか、その過程を記述することを試みた。
その際、患者文化を外部からの視点で記録するのではなく、今なお療養所という場に生きて生活している人々の語りを通じて、彼らの中に生き続けている記憶を記述することを目指した。このような目的のために、特に注目したのがM.アルヴァックスの定義した集合的記憶という概念であった。集合的記憶とは、特定集団の生活世界のなかでかたちをなし、集団の実践的活動とともに可塑的に変化しつつ存続し、集団の消滅によって消えてゆくといった、集団の生活史から生まれてくる共有された意味体系である。本書ではアルヴァックスがイメージや観念からなる集合的な記憶の枠と位置づけたものを、人々がモノ・コトを理解するために用いる記号的なルールの体系(文化コード)と捉え直して用いている。
【構成内容】
上述の意図に沿って、本編は三部構成となっている。
まず第一部『生活の語りからみる患者文化の諸相』では、患者集団の集合的な生活活動がもたらす創発性、および文化形成について論じた。そもそも日本のハンセン病療養所では、自分たち自身の生活を保障するため、患者たちによって、患者自治会、県人会、宗教団体、居を共にする舎の仲間など、様々な社会関係や生活組織が生まれていた。これらのしくみは最初からそれを組み込んで療養所管理が計画されたというよりは、患者たちが療養生活のなかで必要に迫られて組み立て、持続的な形態へと発展させていったものである。従来、合理的に管理された全制的施設において被収容者たちの組織的な活動は不可能だとされてきたが、それを可能とした構造について考察し、今も療養所で暮らす人々が生活をどのように意味づけているのかについて検討した。すなわち、療養所の生活について語ることは、施設という場所を、いかにして患者たちの生活の場として作り替えていったのかについて語ることでもある。もちろん語りは患者一人一人の解釈によって紡ぎ出されるものであるが、どのように生活したかという語りは、活動を共にした集団の視点を通して自らを振り返るものとなる。そして今もそのように語られるということそのものが、現在の語り手の生活においてもその記憶の枠が有効に働いていることを示している。そこで第一部では、患者たちの語りから、彼らが共有している集団の文化コードを探しだし、患者文化とは何かを明らかにすることをめざした。
第二部『患者集団の記憶の枠に寄り添い離れつつ語る自己』では、患者たちの自己物語の語りにおいて、患者集団の記憶の枠がどのように用いられているのか、その実態を読み解くことがねらいであった。ここでいう自己物語とは、語る〈今・ここ〉の時点における状況に準拠しつつ、語り手がこれまで生きてきた過去の軌跡(人生)について語る語りのことである。集合的記憶との関連でいえば、人は人生の軌跡のなかで様々な集合的記憶を集積してゆくのであり、個人とは集合的記憶が交差する地点であるといえる。ゆえに人が保持している集合的記憶は必ずしもひとつとは限らず、ある集団への参入は新しい記憶の獲得機会でもあり、一方で集団からの離脱はその記憶の忘却を意味する。人という個体の履歴のなかで、様々な集合的記憶が獲得され、作用し、そして忘れ去られてゆく。ゆえに個人的記憶とは固定的で一貫したものではなく、個人の生活史のなかで伸び縮みする可変的で流動的なものである。さらにいえば人はある一定のポジションから一貫した物語を常時表出するというよりは、その人の特定集団内の位置、また他の諸集団への準拠の度合いに応じて、様々な集合的記憶をアレンジして状況に即した自己を表現していく。このように集合的記憶論から患者たちの自己物語の語りを捉えてみると、その語りは多様である。あるときは同じ境遇の仲間との相互行為を通して意味を共有し、みずからの個別的な経験を再解釈するために、患者集団の集合的記憶が用いられることもある。その一方で患者集団の集合的記憶を批判的に用いて説明することもあれば、より適した表現方法を求めて異なる外の集団へ参加し、新しい集合的記憶を手に入れることもある。第二部では出産をタブーとする患者社会の中にあって子供を産み育てた女性、当時としては珍しい恋愛結婚による園内結婚にて今も療養所で暮らす一組の夫婦、家族内感染によって父親と共に入所してきた男性、在日朝鮮・韓国人ハンセン病患者であり裁判では原告として闘った男性、これらの5人の語り手たちの語りを取り上げた。
最後に第三部『消えゆく患者集団の記憶の果てに』では、患者文化がどのように終焉をむかえようとしているのかを、療養所の外部あるいは上位に位置する広域的な社会と関連させて分析した。長きに及んだ隔離政策のなかで、療養所に影響を与えた歴史的な出来事はいくつも挙げられるが、本書においては国民のハンセン病政策に対する見方を変えたハンセン病国賠訴訟に注目した。ハンセン病訴訟とは人間としての尊厳の回復を掲げ、すでに隔離収容を必要としない時代になってもそれを改めることのなかった国に対して損害賠償を求めた民事裁判のことである。
その一方で90年近くに渡った隔離政策によって、患者組織と管理運営組織は深い相互依存関係のもとで互いに共振しながら発展を遂げてきた。そのためこのような関係に変化をもたらすには、原告弁護団、運動支援組織といった外部からの介入によらなければならなかった。訴訟運動は新聞やテレビといったマス・メディアを活用して、自らの主張を効果的に宣伝し、法制度というシステムに則って自分たちの主張が政治的に正当であることを示そうとした。従来のハンセン病政策を人権という視点から捉え直したこの運動は、療養所を一般社会へと再統合させるという大きな成果を産んだといえる。ところがこの出来事はこれまで継承されてきた患者集団の記憶に変化を迫ることになり、患者たちは当初、とまどいをもって対処の方針を模索していた。第三部では広域な社会におけるハンセン病に対する認識が変容していくプロセスを記述すると共に、その変容の影響によって衰退し、書き換えられていく患者集団の文化について考察した。
【おわりに】
本書の最後に、患者という下位集団における文化形成はいかにして可能だったのか、そして、下位集団の文化が他の優位な集団あるいは全体社会へ与える影響について一定の考察を示した。
E.ゴフマンは、全制的施設を一般社会とは別様な生活空間であると定義し、その管理システムが、被収容者からあらゆるもの剥奪して、被収容者としてのアイデンティティを付与すると考察した。本書で取り上げたハンセン病療養所でも、これと同様の結果が観察された。しかし、それだけにとどまらず、患者たちによる生活活動は全制的施設に新たな文化を生成させていた。つまり患者たちは、収容以前に暮らしていた村落社会での生活組織の枠組みを療養所に持ち込み、環境に合わせて発展させていたのである。これらの活動は、蜂起や運動といった目に見えるあからさまな抵抗とは違って、取るに足らない日々の暮らしにおける活動を通して行われていた。つまり下位集団の創造性と独自性は、必ずしも機械的な対立によってではなく、従属そのものによる相互依存の深化を通じて発揮され、時には全体社会の文化的コードをも変化させていったのである。ハンセン病療養所の患者文化は、下位集団の従属と創造の弁証法による実践的な力を示している事例であった。