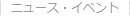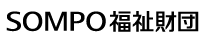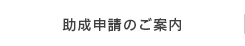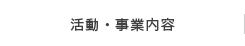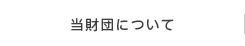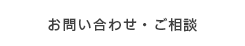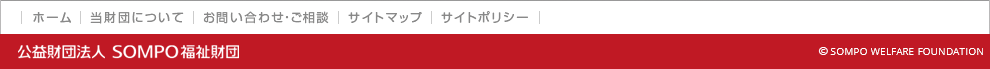第26回SOMPO福祉財団賞 文献要旨
『障害と所得保障−基準の管理から分配の議論へ』
関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科准教授 風間 朋子 氏
1.本書の目的と背景
本書の目的は、障害者を対象とした所得再分配に用いられる基準の設置根拠について明らかにすることである。その基準が何を指標として所得保障の対象となる障害者を選別し、その障害者の障害等級(障害程度)を認定したのか。これを明治初期から国民年金法公布までの約90年にわたる長期的過程において、障害年金制度を中心に追跡してきたのが本書である。
障害者に対する所得保障には公的年金や労災補償があるが、その支給に際しては、障害程度の軽重によって障害状態(主に機能障害の状態)を序列化した基準(主として等級表)が用いられている。この基準によって、所得保障の対象となる障害者が選定され、障害の程度に応じて障害等級が割り振られ、その等級が上位であるほど支給額が高額になる仕組みとなっている。
このように、日本の所得保障制度においては、障害者の稼得能力ではなく障害程度の軽重を基準とした分配が行なわれる。これについて、その基準が医学モデルであることを理由とした批判がある。たしかに、現行の基準は医学モデルであると判断されうる。しかし、このことは、医学モデルの障害観によって基準が生み出されたことと同義ではない。この基準が、障害観とは別の要因によって制度内に組み込まれているのであれば、障害観の変化を理由として、基準の変更を促すことは困難であると考えられる。既存制度の変革を望むのであれば、なぜ、このような基準が採用され、継続されているのかを知ることからはじめる必要がある。
2.研究方法
本書では、明治初期から国民年金創設までの期間、障害年金制度を中心に追跡を行なった。そこで注視されたのは、それがどのように移り変わったのかといった出来事の推移ではなく、その出来事を生み出したメカニズムと構造である。これを行なうには、制度を長期的に追跡し、かつ、そのダイナミクスを分析する必要があった。そのために本書では、歴史的制度論者によって用いられる経路依存、同型化、斬新的制度変化といった概念を援用した。
この分析にあたり、本書では、以下4つの定義を用いて、障害者を対象とする所得再分配の基準を整理した。
- ①稼得能力基準:上位の等級を日常生活動作の自立度、中位以下を個人の稼得能力の減退の程度を指標として、障害状態を序列化した基準
- ②日常生活能力基準:機能障害の程度と日常生活能力の程度が関連していることを前提に、日常生活能力の程度を指標として障害状態を序列化した基準
- ③労働能力基準:機能障害の程度と一般的な労働能力の程度が関連していることを前提に、一般的労働能力を指標として障害状態を序列化した基準
- ④機能障害基準:主に機能障害の程度を指標として障害状態を序列化した基準
3.本書の概要
第1章では、障害者を対象とした所得保障制度に関する先行研究の到達点を示し、本書の知見がそれにどのように貢献するものなのか述べた。併せて、本書の分析枠組みについて、解説した。
第2章では、機能障害基準の汎用化のプロセスを確認した。身体的犠牲の度合いで序列化された軍人対象の公務傷病の等級が、公務員という共通点を持つ他の職種(文官や公立学校の教職員等)にも共有され、やがて、恩給法制定によって統合された。近代医学の最先端にあった軍医が係わる基準が、長期的な運用実績と正統性を有したことで、職種を問わず誰に対しても適応可能な使い勝手の良い機能障害基準の創設が導引された。
第3章では、非官吏公務員を対象とした稼得能力基準が創設されるプロセスを確認した。稼得能力基準の原点が、明治初期に設けられた非官吏に対する公務傷病の補償制度にあり、その基準が国有鉄道や官営工場の労働者を対象とした官業共済制度に引き継がれた。殖産興業を背景に官営工場等の労働者の生活保障が図られるようになっても非官吏は恩給から除外され、独自に保護制度の創設が行われた。このような官吏と非官吏との待遇差別によって、公務傷病の補償の基準が、官吏を対象とした機能障害基準と非官吏を対象とした稼得能力基準に分離した。
第4章では、民間労働者の補償における機能障害基準と稼得能力基準が混在していくプロセスを確認した。非官吏に用いた稼得能力基準を継承した鉱山・工場の労働者の労災補償であったが、等級判断に起因する労使間での紛議の多発を理由として、紛議抑制を目的とした機能障害基準が併設された。これにより、等級表内に機能障害基準と稼得能力基準が混在するようになったにも関わらず、同基準は機能障害基準であると標榜された。
第5章では、稼得能力基準を建て前とした公的年金制度が創設されるプロセスを確認した。機能障害基準と稼得能力基準を内包しながら、機能障害基準であるとされた工場法の基準が、労働者の生活保障を目的とする厚生年金保険に移され、障害給付は稼得能力基準によって実施されるとの建て前が形成された。これにより、障害年金制度の創設時点で、給付の目的と給付の基準との間に乖離があることを前提とした制度設計がなされた。
第6章では、稼得能力から(一般的)労働能力への指標変更によって労働能力基準が創設されるプロセスを確認した。戦後、労災補償の障害補償と厚生年金保険の障害年金との連結が強く意識されたことで、両者の等級間の対応関係がこれまで以上に求められた。しかし、機能障害基準を標榜する労災補償と稼得能力基準を建て前とする厚生年金保険は、見かけ上は異なる指標を持つ基準となっていた。その両者に整合性を持たせるため、両者の指標は一般的労働能力であったと再解釈する方法が取られた。
第7章では、労働能力の量的評価方法の獲得によって労働能力基準が安定化するプロセスについて確認した。厚生年金保険の障害給付において、認定業務の標準化のために労働能力の評価方法の整備が希求され、これによって障害認定基準の併設が導かれた。障害認定基準の設置にあたり、労災補償の補償費の日数によって労働能力の評価を行なったことで、労働能力基準の安定的な運用が可能になるとともに、労働能力の程度により機能障害の状態が配置されたとする解釈が強化された。
第8章では、厚生年金保険と身体障害者福祉制度の等級間調整によって日常生活能力基準が創設されるプロセスを確認した。障害厚生年金を範として構想された国民年金の等級表が、最終的には身体障害者福祉法施行規則の等級表からの強い影響により変質したことで、現行の障害基礎年金にも継承される日常生活能力基準の誕生が導かれた。国民年金の等級表は、厚生年金保険による労働能力基準と、身体障害者福祉法施行規則の等級を用いた制度対象者の簡便な確認方法との調整の場となったが、特に、初年度に大量の裁定業務が発生する無拠出制障害年金の対象となる国民年金1級(障害福祉年金)において、身体障害者福祉法施行規則の等級表1・2級との正確な対応関係が優先されたことを明らかにし、このことが、身体障害者福祉の行政解釈で用いられていた日常生活能力概念の国民年金への流入を導いた可能性を指摘した。
4.結論
本書では、障害者を対象とした所得再分配の基準は、障害によって稼得能力がどの程度減少したのか、その評価方法の模索ではなく、障害者の合理的な管理、つまり、多数を画一的に障害認定するための効率的で標準的な障害認定方法の追求によって展開が促されてきたことを明らかにした。困難が予想される稼得能力の評価方法の模索は早々に破棄され、標準化を目的とした障害認定技術の洗練が図られてきた。現在の障害年金制度で用いられる基準の原型は、稼得能力の推定とは無関係に設置されたものである。起点となったその基準は、その時々の行政側の都合によって読み替えられ、無批判に継承が繰り返されてきた。したがって、そもそも稼得能力を反映しない概念として設定された労働能力や日常生活能力の評価方法を洗練させたとて、両概念に基づく評価方法によってでは、実質的な障害者の所得保障を果たし得ないということになる。
本書は、関西学院大学の出版補助(2023年度)を受けて出版した(関西学院大学研究叢書第260編)。