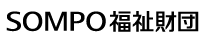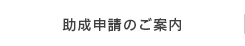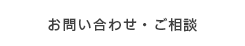第13回損保ジャパン記念財団賞 受賞文献要旨
[著書部門] 『ボランティア』の誕生と終焉-<贈与のパラドックス>の知識社会学
法政大学社会学部 准教授 博士(教育学) 仁平典宏
本書は、日本における「ボランティア」言説の成立・変容過程を、明治後半から2000年代に至るまで知識社会学的に分析し、その社会政策的・政治的含意を検討したものである。
「ボランティア」という言葉は、賞賛と共に偽善ではないかという冷笑を呼び起こす。この二重性は、ボランティア概念の中核にある〈贈与〉という要素に起因する。〈贈与〉は与える/受けるという非対称的な関係を発生させ、受け手を従属的な位置に置く暴力的な位相を持つ。本書ではそれを〈贈与のパラドックス〉と呼んだ。ボランティア言説の歴史は、この〈贈与のパラドックス〉をいかに解決するかの歴史でもあった。それが本書の記述対象である。
戦前は、明治期の「慈善」から大正期の「奉仕」へ、さらに昭和初期の「奉公」へと転換する。「慈善」言説においては、無私を徹底し〈純粋贈与〉へと近づくことが望ましいとされた。これとは逆に、大正期の「奉仕」では、「社会」を媒介して相手のみならず自分の利得も向上させることが強調された。これは〈贈与〉の危うさを、〈交換〉に近づけることで安定させる営みでもある。だが、昭和の戦時期には再び、「滅私奉公」の語に象徴されるように、強度の無私を―自分の命に至るまで―求める言説が社会を覆うことになる。
戦後改革から1970年代に至るまでは、〈贈与のパラドックス〉の解決を、社会的・政治的なレベルを参照しながら行う事が重視されていた。具体的には、国家から自律していること(民主化要件①)、国が行うべき社会保障を代替しないこと(民主化要件②)が、ボランティアにとって重要な基準となる。ここには戦前の反省がある。つまり、国から動員されるまま奉仕を行うことや、国が社会権保障を放棄した状態で慈善にいそしむことは、結局は被援助者を困難に追い込むことになり、自己満足的な行為となる(〈贈与のパラドックス〉を発生させる)という痛切な記憶があった。だからボランティアはミクロな相互行為に自己完結してはならず、制度の改善を求める政治・運動にも繋げることが重要とされた。これは、特に大阪ボランティア協会など、民間の草分け的なボランティア中間支援組織には強烈に意識されていた。この思想が最も花開いたのは、1970年代の障害者の自立生活運動においてである。
一方で、1970年代は戦後のボランティア言説の転換点でもあった。ボランティア政策の開始と社会保障費の増大の中で、①②の要件が相対化されると同時に、ボランティア自身の「自己実現」や「生きがいづくり」が重視されるようになる。つまり再び、ボランティア言説からマクロ政治的基準が捨象され、ミクロな相互行為のみがその対象とされていくわけだが、この背後には貧困から人間疎外へという社会問題観の変化も影響していた。
1980年代以降は、高齢化社会への対応という文脈でボランティア活動の育成が本格的に進められる。そこでは、担い手の楽しさ=精神的報酬の強調や、有償ボランティアや教育評価への導入などが進むが、これはボランティアを〈贈与〉ではなく〈交換〉的行為として再定義する流れである。自らを〈交換〉と予め位置づけておけば、偽善という批判を無効化できるという意味で、〈贈与のパラドックス〉の洗練された解決でもあった。だがその帰結として、「ボランティア」の同一性が掘り崩され、空虚な記号と化していくと同時に、経営的合理性と結びつくことで〈交換〉の徹底に成功した「NPO」に、参加型市民社会の中心的なカテゴリーの位置を明け渡すことになった。
2000年代には、ボランティアやNPOが、ネオリベラリズム的な福祉抑制の文脈に接合された。しかし政治・運動への回路を消失した現在のボランティア言説は、もはやそれに抗う足場を持たない。必要なことは、〈贈与のパラドックス〉の解決を、経営論/自己実現論的地平に限定せず、制度・政策の改善という政治レベルも経由しながら試行する強靱さである。