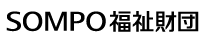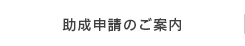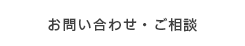第11回損保ジャパン記念財団賞 受賞文献要旨
[著書部門] 『チャリティとイギリス近代』
京都大学大学院文学研究科 准教授 金澤周作
18世紀半ばから19世紀後半のイギリスは、工業化の過程で、持てる者と持たざる者の間に厳然たる溝の穿たれた階級社会、弱者を切り捨てる過酷な世界になっていったとされる。ところが、その近代イギリス社会は、途轍もないエネルギーをチャリティに傾注し続けた。それを実証的に解明し、歴史的な意義を探ることが本書の課題であった。
第一章では、チャリティの種類と規模を再構成した。全てのチャリティ的行為の基盤にあるのは、物乞いへの施しのような個人による直接の援助(個人型)。地域共同体で続けられる、落ち穂拾い等も盛んだった(慣習型)。さらに、全国で数万存在した養老院や学校のような、基本財産によって半永久的に維持されるものがあった(信託型)。ちなみに、信託型を管轄した法や制度は、現在では、意味内容を大幅に拡張した「チャリティ」全般を司っている。次に、より新しい形態として、「動物虐待防止協会」のような、募金を収入源とするものがあり、19世紀半ばのロンドンだけで500以上もあった(篤志協会型)。最後に、この型の変形として、労働者の互助会を後援するもの(友愛組合支援型)。以上の5つの形態が、モザイク状に重層的に広がっていたのである。
第二章ではまず、かかる種類と規模を有するチャリティが、「当局」の行う公的な救済といかなる関係にあったのかを論じた。16世紀末から展開していた救貧法行政(末端の行政単位である教区が、徴収した税で貧者を救済する)は、チャリティを前提としなければ成立し得なかったことを示した。続いて、海難救助における国家と民間の関係を検討した。海上保険はあくまで財にかけられるものだった。法も財の救助しか規定しなかった。人の救助は、18世紀末から一連の発明がなされて、陸から海へ救助に向かえるようになってはじめて可能になった。しかし、人命救助を主として担ったのは国家ではなく一チャリティ組織だったのである。最後に、イギリス本国と帝国(インド)とで、チャリティの意味が異なるという事実に注意を促し、近代イギリス本国におけるチャリティが、自由主義や夜警国家のイデオロギーと親和的であったことを指摘した。
第三章では、チャリティ社会を生きた人々の経験をとらえようとした。王族、地域有力者、富裕者、女性、受け手、イギリス人にとっての、チャリティの意味と機能を確認した上で、全体として、多様なチャリティ活動が、救い・救われる安定した「共同体」の理念を具現し、また、その理念を再生産するかのように、次々と新しい「悲惨」が創出され、対処されたと論じた。そして、この社会では、チャリティの存在意義を否定する主張は力を持ち得なかった事情も説明した。とはいえ、20世紀には国家福祉が台頭してくる。その転換に際し、チャリティはどのような圧力を被ったのか。本書は、寄付者が救済対象者を選挙で選ぶ「投票チャリティ」という一見奇妙だが実はチャリティの典型といえる事象に焦点を合わせ、この方式が世紀後半に、後の国家福祉の発想に近い論理で激しい批判を浴びたにもかかわらず、第二次世界大戦頃まで生き残った経緯を述べ、チャリティの倫理の強靭さを示した。
かくして、近代イギリス史にとってチャリティは本質的な要素であった。また、チャリティは20世紀の国家福祉構築の過程において、排除されるどころか、不可欠なものとして前提される。理想的とは言えないが国家福祉と民間のヴォランタリズムが共存するイギリスの現在を理解するためにも、本書の議論が何か参考になればと思う。