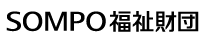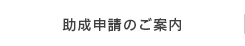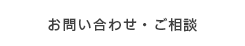第5回損保ジャパン記念財団賞 受賞文献要旨
[著書部門] 『社会福祉における資源配分の研究』
立教大学コミュニティ福祉学部 教授 社会福祉学博士 坂田 周一
本研究は政府部門の資源制約が顕在化した1980年代から2000年までの期間を対象として、わが国の社会福祉供給体制に生じた変化の要因を資源配分の観点から検討したものである。この変化は、わが国の社会福祉にとって根本的なものであり、多様なアプローチからの検討が求められる歴史的な重要性をもっているが、その解明に一定の貢献ができたと考えている。いっぽう、社会的ニーズとそれを充足するための社会的機構がもつ機能を明らかにし、さらには可能な代替案の成立条件の検討を課題とする社会福祉政策研究において、社会的ニーズを中心とする分析と、福祉サービスの供給を中心とする分析の両者を結合する枠組みとして、資源配分における割当(ラショニング)の概念の意義を検討することも目的のひとつとした。
第1章では、1980年前後に顕在化した国家財政の窮状から、社会福祉政策研究において資源配分からのアプローチが欠落していたことを反省する状況があらわれたことを指摘した。
その上で、新たな研究の核として資源配分における「割当」の概念に注目が集まったことを指摘し、その理論的意義を検討した。
第2章から第4章はこの論文の課題を具体的に提起するセクションである。第2章では福祉の供給体制を歴史的に跡付け、わが国おける社会福祉制度の基本的な形がどのようなものであるかを明らかにし、第3章では国家財政の長期的な動向の観察を通じて、政府部門への国民所得の配分と政府部門内部での配分に生じた状況変化および社会保障への資金の配分がどのようであったかを大筋においてとらえたうえで、資源配分問題が福祉改革のモーメントになった背景を検討した。第4章では、公共部門における資源配分の意思決定がコレクティブチョイスを特質とするものであることから、過去に提起された公共的意思決定の規範理論を検討し、資源配分においてインクリメンタリズムが支配的となる論理をめぐって国会会議録の精査ならびに財政データの分析によって検討した。
第5章から第7章までは、資源なかんずく財源の配分を、国家財政内部での社会福祉への配分、国から地方自治体への配分、地方自治体間での配分の順序に従って、分析モデルを提示しデータによる検証を行った部分である。第5章では、国の社会福祉予算が1960年代初頭から80年代初頭にかけて指数曲線の形状をしていることについてインクリメンタリズムによる説明を与え、現実への適合性を高めるために修正モデルを提案した。そのモデルを検討すると80年代中期以降、社会福祉が極めて困難な資源制約に遭遇することが予測され、計画化に向けた政治的・行政的行動の変更が提案された。第6章では、国と地方自治体の関係を形作る構造パラメータの一つである国庫補助率が80年代中期に引き下げられたことの背景と影響を検討した。第7章では、地域格差の問題を題材として地方自治体間での資源配分を検討し、国からの補助金にみられる地域格差が自治体独自の財政活動としての一般財源の投入によって縮小されていることを明らかにした。
第8章と第9章は、社会福祉供給の新しい現象である計画化と有料化について資源配分の観点から分析したものである。第8 章では、90年代における社会福祉の計画化によって、一定の限界内において、自治体内部における財源配分のインクリメンタリズムからの離脱が促進されたことを検証した。第9章では社会福祉における有料化がパラダイム転換と言うべき社会福祉概念の変容と表裏をなすものであること、また、料金徴収が価格機構と同等の機能を果たすには各種の限定が必要であることをあきらかにした。これらの検討を受けて、80年代から90年代にかけてわが国の社会福祉に生じた変化を解釈するために第10章が執筆された、やや長い「あとがき」はこの研究全体を振り返る目的で個人的メモワールとして書かれている。
[論文部門−1] 「母親の虐待行動とリスクファクターの検討
−首都圏在住で幼児をもつ母親への児童虐待調査から−」
*氏名の50音順に掲載
東京都精神医学総合研究所 主任技術研究員 大原美知子
児童虐待防止法の制定により、わが国もようやく虐待の存在が認知され、それに伴い虐待の発見件数も毎年上昇の一途をたどっている。虐待問題を援助する専門機関である児童相談所は虐待件数の増加とそれへの対応・支援に追われ、多くの労力を注いでいるにも関わらず、悲惨な事件は起こり続けている。これらのことから虐待に対してどのように介入・支援するのか、また虐待に至る前に防止できるのか否かの究明は、いまやわが国にとっても大きな課題であるといえよう。
子供への不適切な育児行為を助長しているのにどのような要因が関連しているのか、都市化・核家族化・地域社会のおける絆の弱体化などさまざまな解釈がなされているが、実際に虐待が起こる家族とそうでない家族との間にどのような違いがあるのか、また個別の家族の脆弱性など、虐待のリスクファクターにはどのようなものがあるのかの実証的な検討はあまりなされていない。
本研究は児童虐待の支援に先駆的に取り組んできた社会福祉法人「子供の虐待防止センター」より委託を受け、実効的な対策を立てる上での正確な現状把握、および養育上有害な育児行動のリスクファクターとなっている要因分析を行うために行った、多面的な調査をもとになされた研究である。
調査方法は首都圏在住で満6歳以下の幼児を持つ母親を対象に、層化二段無作為抽出法(調査地点120地点)によりサンプリングを行い、自記式アンケート調査をおこなった。調査内容は母親による子どもへの不適切な育児行為とその頻度、母親自身の生育環境と現在の環境(FES)、母親のメンタルヘルス(EPDS)、解離傾向、母性意識、母親が認知しているサポートなど多面的な質問を行い、虐待行動のリスクファクターを検討した。子供への不適切な育児行為については、内山らの先行研究を元に、虐待母の自助グループ(MCG:Mother and Child Group)メンバーの協力を得、ヒアリングをおこない虐待行為項目を作成した。作成した行為項目17項目を合算し虐待得点とし、その平均値からカットオフポイントを算出し、虐待・非虐待群の2群化を行った。その結果、虐待群は1508名中120名(7.8%)、約8%の母親が該当し、虐待の可能性はほぼ10人に一人の母親が有していることが明らかとなった。
虐待得点にどのような要因が影響を与えているのかを見るために、虐待得点と諸項目を重回帰分析で解析したところ、子どもの数(育児負担)・解離傾向・気の合わない子どもがいる(子どもに対する不適切な認知)・葛藤性(家族内の暴力傾向)・母性意識否定感(母親の低い自己評価)などが虐待行動への影響要因として選択された。これらのリスクファクターは諸外国における先行研究とも一致し、リスクファクターの査定は虐待ハイリスク家族の発見を容易にし、虐待の防止と適切な治療的介入を促進する可能性を有していることが理解された。そして虐待は単独のリスクファクターで生じることは少なく、諸要因が重なる時生ずるといわれている。そのためリスクファクターを早期に発見し、リスクを重複させないような支援が求められるが、それをどう具体化してゆくのか今後に架せられた、早急かつ必要な課題である。
最後にこのたびの受賞に際し、この研究を支えてくださった諸先生方、および多くの皆様に心より御礼と感謝を申し上げます。そして今後とも多くのご指導・ご支援を承ることができますようお願い申し上げるとともに、自らも研鑽に励んでまいりたいと思います。
[論文部門−2] 「生活保護における『母子世帯』施策の変遷
−戦後補償と必要即応原則−」
国立社会保障・人口問題研究所 研究員 菊地英明
現在、新法制定以来50年以上にわたって大改正が行われなかった生活保護制度の改革が検討されている。しかしこの間、生活保護法が掲げる諸原理・原則の根本的な検討は、どこまで行われたのだろうか。また、そもそも生活保護のような直接の拠出に基づかない「必要に基づく社会政策」の道徳的基盤は、いかなるものなのだろうか。本研究は、それらの問いを、戦後期に立ち返って検討する試みである。
生活保護の主要原理の一つである「無差別平等」は、保護の要否認定を、ある者が困窮に陥った過程・原因や、社会的カテゴリではなく、現在の経済的困窮度から判断して平等に処遇することとされ、民主的な公的扶助の指標とされる。だとすると、旧法から新法への改正時に、「必要即応」原則−異なった状況の者に異なった取扱いをする−をなぜわざわざ明文化する必要があったのだろうか。この問いに対して、資料からは以下のことが言える。
(1)GHQは、福祉制度における旧軍人層の優遇を排するために、「無差別平等」原理の導入を要求した(したがってここでいう「無差別平等」は、一般にイメージされる民主主義の原理そのものではない)。
(2)これは、戦争未亡人やその子に対する特別立法を禁止し、すべての困窮者を生活保護の枠内で処遇することを意味した。しかしそれだけにとどまらず、保護内容まで形式的平等にする(状況を問わず、あらゆる者を全く同じように処遇する)ケースが続出した。
(3)彼女たちの苦難の原因が国策=戦争にあるとの認識のもとで、一般困窮者と同様に生活保護の枠内で処遇するのは不当であり、補償の特別法を制定すべきとの声が国会などで次第に高まった。
(4)特定カテゴリの優遇がGHQから禁止されたため、生活保護の枠内で、彼女たちへの処遇を充実して補償に代えるよう、改正が行われた。具体的には(i)「必要即応の原則」の導入=育児する母親に対するニードを反映した特別基準、加算の導入。(ii)「育児は労働である」との論理=保護の補足性原理(市場における稼働)の免除を正当化する言説である。
これは、「戦争未亡人」対策を、生活保護の枠内での「(死別)母子世帯」対策へと翻訳する巧みな言説戦略であり、それを支えた理念が「戦後補償」であった。
従来の生活保護史は、社会運動の果たした役割を強調しつつ、憲法第25条のいう生存権の確立や、生活保護の拡充を説明する、単純な進歩史観であった。しかし本研究で描かれたのは、従来とは別の生活保護像である。すなわち、事前の拠出なしに行われる「必要に基づく社会政策」の代表格とされる生活保護の給付が、それと正反対の「貢献に基づく社会政策」の変種である、「補償による社会政策」への翻訳によって規範的に正当化されたことが示された。
この意味で、必要原理としての生活保護の道徳的基盤は非常に脆弱であった。事実、1970年代以降、他法他施策の充実や離婚の増加などに伴い、生別母子世帯が母子世帯の多数を占めるようになると、彼女たちを「無責任の象徴」と描く差別的な言説が支配的になっていく。しかしこの問題を前世紀的遺物として片づけることはできない。我が国での児童扶養手当の改定や、各国での公的扶助へのワークフェア原理の導入の過程を見るにつけ、純粋な必要原理に基づく給付の規範的正当化、という課題の存在感が、今ますます高まっているのではなかろうか。
ところで、本研究には、言説が制度のあり方や運用を方向づける過程を描くという、方法論的な実験の側面もある。しかし、その実験がどの程度成功したか、心許ないところである。また、今にして思えば、実証の面で必ずしも十分でない点も見られ、その点は率直に反省したい。
最後に、損保ジャパン記念財団賞の受賞に際し、お世話になった先生方に厚く御礼申し上げます。今回の受賞を励みに、研究に邁進していきたいと思っています。
[論文部門−3] 「社会福祉と共生」
清和大学短期大学部 専任講師 寺田貴美代
共生という用語が広範な領域で使用されるようになって久しい。さまざまな分野において、多様な解釈を伴って用いられており、今後の社会福祉を考える上で、極めて重要な概念として提起されながらも、曖昧な定義によって共生概念が用いられることも少なくない。そこで、社会福祉領域における、この概念の意味を明確化し、共生に向かうプロセスを考察することが本論文の目的である。
本論文の内容は、まず前半(第1節・第2節)において、共生概念に関する先行研究を整理し、この概念全体を貫く本質的特徴を概観する。そして、共生概念に対する多様な理解、錯綜した解釈の現実を踏まえつつ、共生に関わる各論の一つとして、社会福祉領域における共生概念を取り上げ、この概念の意味と問題について、先行研究を踏まえて明らかにし、その可能性と課題を考察する。
後半(第3節・第4節)では、自らの試論を提示し、まとめを述べる。マジョリティ文化への志向性と、マイノリティ文化への志向性という2つの軸を組み合わせて2次元の図式を構成して類型化し、分析枠組を構成する。さらに検証結果を基に、文化志向性の変容パターンと、それに伴う生活課題の変化との関連を示した。そして、類型を再構成し、新たに動的な図式を提示した。また、文化志向性は不変ではなく、その変容パターンは、多様化しつつも、時間の経過に伴い、一定の方向性が現れることを指摘した。
さらに、結論部において、共生とは「人々が文化的に対等な立場であることを前提とし、その上で、相互理解と尊重に基づき、自−他の相互関係を再構築するプロセスであり、それと同時に、双方のアイデンティティを再編するプロセスである」と定義している。そして、このプロセスが積極的に展開され、新たな関係の生成・創出と、自らの再編による、ダイナミックな関係を必要とする社会こそ、共生社会であると論じている。
また、本論文では、共生概念の歴史的経緯や変遷よりも、現在の概念が持つ意味を明らかにすることに重点を置き、その意味内容を新たに掘り下げることを試みている。共生概念の精緻化は、この概念の限界を示すと同時に、積極的意義の明確化であると考える。それは、社会福祉領域において、共生概念はどのような可能性を持つのか、可能性を広げることができるのかということを示すだけではなく、共生概念全体が持つ可能性の広がりでもあると考えている。
なお、本論文は、『社会福祉とコミュニティ』(園田恭一編、東信堂、2003)の中の、第2章に収録されており、博士学位請求論文『共生へ向けた支援の展開』(2002年認定)において構築した理論の中から、その一部を抜粋し、単独論文として構成したものである。ちなみに、博士論文全体は、『共生社会とマイノリティへの支援』(東信堂、2003)という書名で、昨年末に出版した。また、本論文の理論を更に発展させた研究としては、「社会福祉が成立する範疇に関する分析枠組の構築」という論文が、『福祉社会学研究』(福祉社会学会学会誌)創刊号(2004/4刊行予定)に掲載される予定である。ご関心をお持ち下さった方は、こちらも併せてお目通し頂ければ幸いである。
末筆ながら、身に余る光栄な賞を頂きましたことを心から感謝すると共に、御推薦下さった方々や、これまで御指導下さった諸先生に、深くお礼申し上げる。